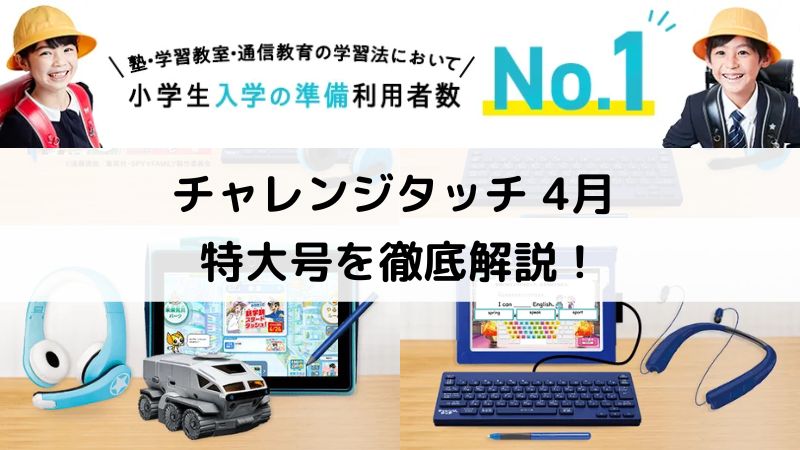和田聖子さんの著書『「算数が得意な子」にするために親ができること』で紹介されていた
高濱正伸先生の著書『小3までに育てたい算数脳』では、図形問題を解く上で必要な空間把握能力をはじめとする算数脳を育むのは「小3までの外遊び」であることが述べられています。
「外遊びで本当に算数脳が育つの?」と漠然とした不安感はありますが、読み進めると理に適う内容ばかりです。
「算数が得意な子」にするために親ができること 161ページ *1
を見て、手許に持っていた高濱さんの『子どもを伸ばす父親、ダメにする父親 』を読み直してみました。そこでは、産まれてから10歳までの時期の成長段階を考慮した「遊び」について説明されています。
「赤い箱」=10歳までの時期は、オタマジャクシの時期、とも言っています。
振り返りが苦手、忘れっぽい、あきやすい、座っていられない、といった「子ども」の特徴がある時期です。この時期の子どもを大人基準で見てしまうと、「何回言ったらわかるんだ!?」とつい叱りたくなってしまいますが、これは絶対にやってはいけないことです。オタマジャクシに何度言っても陸にあがって歩けないように「忘れっぽい」生き物である時期なのです。
「赤い箱」の子どもたちは「繰り返し」が大好きです。大人がもう飽きてしまっても、何度でも「やってやって」とせがまれることもあるでしょう。そんな時に「もういいだろう」と音を上げずに、何度でもつきあってあげてください。
反対に、あきっぽく忘れやすい時期でもありますので、昨日やった遊びに対して、今日はもう興味を示さない、ということも多々あります。それに対して「昨日はこうだったじゃないか!」などど怒ったり、恨みに思ったりもしないでください。
彼らは「オタマジャクシ」なのです。むしろ、日々、変わる彼らの興味関心に、いかに大人である私たちが近づけるか試されているのだと、その変化を楽しむぐらいがおすすめです。昨日うけたギャグが今日受けない…そんなの、子どもの世界では当たり前です。「赤い箱」の時期の彼らの特性をよく知り、それによりそって、遊んでいくことが大切です。
また、『ザ・ギフティッド 14歳でカナダのトップ大学に合格した天才児の勉強法』には日常の生活の中でできる「広い意味での算数学習」についてどのようなことをやっていたかまとめれらていました。
①数を数える
・歩けるようになったころ(1歳)、散歩に行って階段を上るときに数を一緒に数えるようにしていました。
・おはじきを「1つ、2つ、3つ…」というように数えて遊んだりもしました。
・100玉ソロバンを与えて、遊びながら実体としての数の感覚を掴む
・幼児の場合、数字で考える前に、実体を伴った形で数を意識するというのが向いています。
②5を一塊と意識する
・鉛筆を並べて数を数える
・5本をセットにして並べて数える
・小さな正方形の厚紙を使い、5を一塊として意識するという遊び
③積み木、パズル、タングラム遊び
・通常の木製の積み木
・1から100まで数字の書かれた100個の積み木を使って、数えながら遊ぶ
・パズル遊び
④算数プリント教材
・3歳から公文を始める
⑤九九の歌
・九九の歌を教える
ザ・ギフティッド 14歳でカナダのトップ大学に合格した天才児の勉強法
201ページ *3
外遊びといえば、以前から注目している男の子のことが思い浮かびます。サッカーの才能を見いだされFCバルセロナ(バルサ)の下部組織に入った久保健英くん。彼のお父さんの著書に建英くんが幼少期にやっていた外遊びの様子が書かれています。この外遊びの徹底ぶりがものすごい。名門のバルサに入れた理由がわかり、納得させられます。
第2章、第3章外遊びと読書で、体幹とメンタルを鍛える
・徹底的に外遊びをすること(自主保育、幼稚園)
・五感を刺激すること
・自然の中で、生き物にたくさん触れさせる
自然の中で、ぞんぶんに遊ぶことができた3年間でした。なかでも、蝶やバッタ、とかげやカナヘビといった生き物にたくさん触れたことが大事な体験になったと思います。建英は、生き物を追いかけるのが大好きになりました。カナヘビやとかげを見ると喜々として捕まえ、必ず家に持ち帰るものですから、妻は「よく捕まえたね」と言いつつ、決して近寄りませんでした。
・家におもちゃは置かない
「外遊びをするためには、家の居心地がいいとダメ」
・楽しいと思えることを増やすこと
・絵本の読み聞かせで想像力と集中力をつける
・小さいうちはテレビをつけない
・最初に、片足で立てるようにする
・はだし歩きで足裏の感覚を鍛える
・ベビーカーを使わない
雨の日はかっぱを着て、雪の日は重ね着をし、暑い日は水浴びをさせ、サッカー以外にも、たくさんの遊びや経験をさせてきました。
妻は、毎朝3食分の支度をして、建英と一日中外に出ます。
大変だったのは妻でした。
おれ、バルサに入る! 2章 3章 *4
『プレジデントBaby 2013完全保存版―0歳からの知育大百科 (プレジデントムック プレジデントBaby)』の「三歳までに平均台、ボール遊びがなぜ重要か?」では、平均台、ボール遊び、鉄棒ぶら下がりといった運動能力テストが幼稚園の入園試験で実施されている理由、運動をすると頭が良くなる理由、家庭で親子でできる運動の仕方についてまとめられています。幼児教室や運動学の専門家の解説は目からウロコの内容でした。
幼稚園の入園試験で運動能力テストが実施されている理由について
「幼稚園は『基礎的な身体力』に加え、『心の発達』を見ているのです。幼稚園の試験で出るような運動は、特別に難しい訓練が必要な運動ではありません。ではなぜ、その比較的易しい運動をさせて選考しているかというと、運動の技術だけではなく、先生の指示を聞いて理解できるか、指示を守れるか、やり遂げられるか、といった子どものさまざまな能力がわかるからなんです。」
「運動というと、単に体力や運動神経を向上させるためにするものと思われがちですが、集中力、コミュニケーション力、さらには決断力、物おじしない力(胆力)、自信など、実に多くの力を伸ばすことができます。幼稚園受験の運動テストでは、そういう子どもの心の成長も見ているのです。」
「たとえば、出題率の高い課題に平均台があります。細い台の上で歩くには、前に出した足を軸にして、一瞬、片足で立たなければなりません。片足で立つためには、足腰の力とともに、『落ちないようにしなきゃ』と集中する力が必要ですし、落ちたら怖いのでやりたくないという気持ちを克服することによって、胆力も養われます。よく出題されるボール遊びも同じです。ボールを上手にキャッチするには、タイミングに合わせて手足や目を動かさなくてはなりませんが、その際も集中力や、どのタイミングで動けばいいのかを考える思考力や決断力が必要です。」
また運動から得られるものとして、達成感もあるという。平均台を例にとれば、最初はグラグラと体が動いて落ちてしまっても、何度か繰り返してできるようになれば、達成感とともに自分への信頼感にもつながっていくのだ。
「子どもにとって『やればできる』という感覚は経験しないとわからないことです。その点、運動は達成感を実感しやすいものです。子どもは運動で小さな達成感を積み重ねて味わうことで『やればできるんだ』ということがわかるようになります。また、周りから『すごいね!』『できたね!』と認めてもらえれば、英雄体験にもなります。それが自信につながるわけですね」
プレジデントBaby 2013完全保存版―0歳からの知育大百科 (プレジデントムック プレジデントBaby) 128ページ
というように幼少期によく体を動かすことの大切さが 述べられ、「運動神経のベースを作る親子プログラム」プレジデントBaby 2013完全保存版―0歳からの知育大百科 (プレジデントムック プレジデントBaby) 136ページ *5
まで紹介されています。
算数・数学教育からちょっと飛躍してしまいました。
とにかく、幼少期から外遊びなどで体を動かすことが学力の基礎となるということを親としてよく覚えておこうと思います。
今日のちぇぶちゃん
この連休中は自分とちぇぶちゃんとで朝から近くの公園に散歩に行っています。。
今日は妻も一緒に。風が冷たかったのに、ちぇぶちゃんは歩くのが楽しくてしょうがないようでどんどん先を歩いていきます。転んでも気にしないみたい。家にこもっているよりは気分も解放されるようです。
この後は親子でバランスボール遊びをしてみようかな。