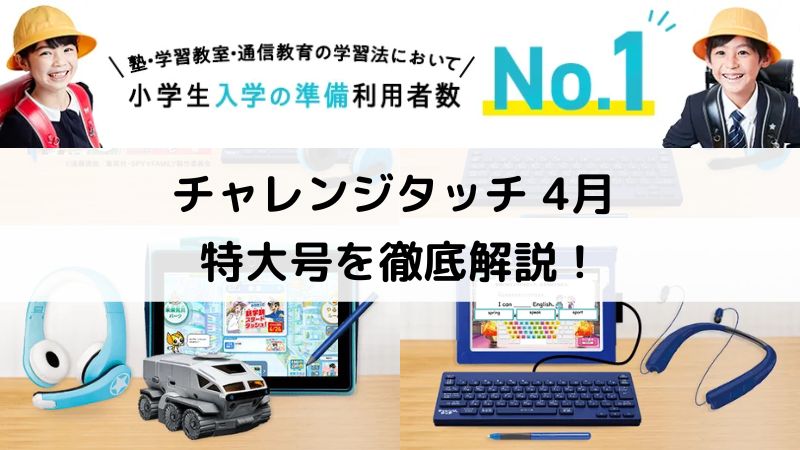わが家の娘ちぇぶちゃんは、2歳3か月から「プリント」や「ワーク」といった幼児教材を始めました。現在は3歳6か月(2017年5月時点)で、教材を使った学習を始めてから早いもので1年以上経ちました。
教材を遊びのようにすすめたり、絵本にたくさん触れることによって、色や形がわかるようになったり、ひらがなやカタカナやアルファベットが読めるようになって絵本も自分で読むようになったり、数が数えられるようになったり、さらには鉛筆を持って線を引いたり字が書けるようになったり…… ちぇぶちゃんは、本当にいろいろなことができるようになってきました。
これは、0歳からの絵本読み聞かせに加えて、2歳3歳という年齢でも「まだ早すぎる」と諦めずに、プリントやワークを継続してきたからだと思います。
今回は、新年度が始まってキリがいいので、プリントやワークといった知育教材の選び方や始め方について、パパなりにまとめておこうと思います。(この記事は 2017年5月時点に投稿されたものです。)
- ポピーのお試し教材
- お試しワーク(約7~10日分)
- ポピーからのお知らせ(親向け資料)
- 家庭教育の手引き
この3点が無料体験でもらえます。
2週間分のワークがたっぷり体験できるので
気軽に取り寄せてみてくださいね。
豪華な紙工作ふろくつき

▼知育の記録、記念すべき第1日目
いつから始めるか
プリントやワークを始めるということは、紙にシールを貼ったり、クレヨンや鉛筆で線や文字を書いたりする作業をすることになります。ちぇぶちゃんの生後すぐに絵本の読み聞かせをスタートして、1歳前半で「ABC」や「あいうえお」、「123」に強い興味を持つようになったため、型はめパズルやアルファベット、数字のおもちゃでたくさん遊んだちぇぶちゃん。そのおかげかどうかわかりませんが、特にひらがなやアルファベットや数字が大好きになりました。
このころがプリントやワークを始めるのにいいタイミングだろうということで、ちぇぶちゃんは2歳3か月からプリント学習を始めました。
2歳3か月といえば、イヤイヤ期真っ只中。理由もなくイヤイヤしたりかんしゃくを起こしたりすることもあり、プリントをやるのが大変な時もありましたが、1枚あたり1分(長くても5分くらい)で終わるというのが良かったのか、何とか続けることができました。
また、2歳くらいだと「お勉強」と「遊び」の区別もつきにくい時期で、この頃に始めたのは「プリント=遊び」というイメージを持たせることができて正解でした。今でもプリントがお勉強だとは思っていないようです。
遊びの一環で楽しく取り組んできたおかげで、娘が絵本やプリントの文章をスラスラと自分で読んでいく姿には成長を感じます。
まとめると、
- 生後まもなくから絵本の読み聞かせ。
- 文字や数字に興味を持ったら、型はめパズルなどの知育玩具を遊びに取り入れて、アルファベット、ひらがな、数字、形、色に慣れ親しむ
- 文字や数字が好きになったところで遊びの延長としてプリントを始める
という感じで進めていくのがいいのではないかと思います。
どの教材にするか
次にプリントや幼児教材はどれを選べばいいかという点について考えてみます。
遊びのようなものとしてプリントをやるといっても、そこは2・3歳児。集中力がなかなか続かない子どもが毎日プリント学習を継続するのは大変です。
そこで、子どもが続けやすい工夫が凝らされているもの、ということで
- 白黒ではなくカラー
- シール貼りをしながら回答できる
- 毎月1回1か月分の教材が届く
- 子どもとの相性が合うもの、難しすぎず易しすぎない、難易度がちょうど良いもの
という条件を満たす教材がおすすめです。
白黒ではなくカラー
幼少期は色や形に大きな興味を持つ時期なので、教材も白黒のものよりはカラーのものの方がふさわしいと思います。(とはいえ、娘は白黒教材でも気にせず集中して取り組んでいたので、相性が合うようなら白黒でも良いのかもしれません。)
シール貼りをしながら回答できる
子どもがプリントをやるという場合、まだ鉛筆などで思うように書けないのが普通。それにも関わらず、「書く」箇所がたくさんあると、なかなか上手に書けないのでプリントが嫌になってしまいます。そこで「書く」ことに苦手意識がなくなるまでは、シールを貼って回答するタイプの教材がおすすめです。
ただ、シールを台紙からはがす作業も2歳くらいだとなかなか難しいようです。ちぇぶちゃんも3歳になってからようやく自分ではがせるようになりました。
そのため、「書く」にしろ「シールを貼る」にしろ、なるべく親が側でサポートしながら進めていく必要があります。
毎月1回1か月分の教材が届く
初めから全部揃っている教材を1から順に進めていくのと、4月号、5月号、6月号…と毎月届く教材を進めていく場合とを比較すると、後者の毎月1回1か月分の教材が届けられる方がヤル気が続くと思います。
- 4月号が届いた!
- 4月になったら4月号をやろう
- 4月号終了!
- 5月号が届いた!
- 5月になったら5月号をやろう
- …
というサイクルで、毎月届くタイプの教材の方が継続させるという点では優れていると思います。わが家では、ポストに教材が届くと、さりげなく娘が見つけて持ってきてもらうように心がけています。ちょっとしたことですが、毎月本当にうれしそうに「○がつごうの○○がとどいた~!」と言いながら持ってきてくれます。
子どもとの相性が合うもの、難しすぎず易しすぎない、難易度がちょうど良いもの
あとは、実際に教材の見本を手に取って見たり、お試し受講して見たりして、子どもとの相性が合うかどうかじっくりチェックすることも大切だと思います。パッと見、よく見えたとしても、実際にやってみると思っていたものと違った... なんてことはよくあること。親ではなく、あくまでも子どもと相性が合う教材かどうか冷静に判断していく必要があります。
いちばんのおすすめは…
わが家でもいくつか教材の資料請求をしたり見本を比べたり、実際に受講してみたりしましたが
- 幼児ポピー「きいどり」「あかどり」「あおどり」
- 七田式プリントA、B、C
- Z会幼児コース
の3つがとてもよかったです。
特にポピーの教材は、白黒ではなくカラーで、回答の仕方はシール貼り中心で、毎月1回1か月分の教材が届く上に、娘のちぇぶちゃんも気に入っていたので、パーフェクトに近い出来でした。
ちなみにちぇぶちゃんは、インターナショナルスクールに通う前は、幼児ポピー「きいどり」、七田式プリントA、Z会幼児コースの3つを進めていました。スクールに通うようになってからは、さすがに負担が大きすぎるということで、幼児ポピー「あかどり」と七田式プリントAに絞って進めています。
わが家の場合、日本語のプリントについては、主にパパがそばでサポートするようにしています。また、絵本の読み聞かせや英語については、ママが強力にサポートしてくれています。どちらもできるだけ親子で楽しく会話をしながらすすめています。
まとめ
…というわけで、2歳・3歳からの知育教材の選び方と始め方のポイントについてまとめてみました。
今後どういったものに取り組んでいくのかという点については、ちぇぶちゃんの様子を見ながら改めてじっくり考えていくつもりです。
弟のだっくんがプリントを始めるのはまだ先の話ですが、ちぇぶちゃんのときの経験を活かして、上手に進めていこうと思っています。
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 月刊教材ポピー |
980円(/月)
|
|
七田式(しちだ)プリントA |
1192円(/3冊)
|
全30冊のうちの3冊分
|
| Z会 幼児コース |
2200円(/月)
|
|
【こどもちゃれんじ】 |
2379円(/月)
|
(2、3歳向けぽけっと)
|
|
800円(/月)
|
|
※関連記事
▼2歳3か月でのまとめ
▼現在受講中のZ会幼児年長コースの最新号はこちら
▼現在受講中のこどもちゃれんじ じゃんぷ最新号はこちら
▼現在受講中の幼児ポピー あおどりはこちら